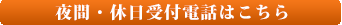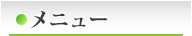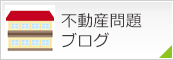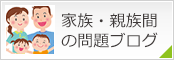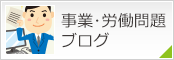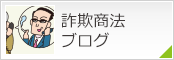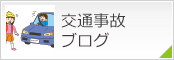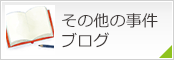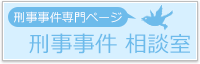交通事故(被害者側4)
- 2017年01月28日
- 交通事故問題の事例
◆ 事件の内容
依頼人は,交通事故により,自賠責保険の後遺障害認定手続において,「後遺障害14級」の判断を受け,これを前提として,加害者に裁判を起こしていました。
しかし,第1審の裁判所は,後遺障害認定の前提となった「腰椎捻挫」については,本件事故による受傷とは認められないとして,本件事故と後遺障害との因果関係を否定しました。
その結果,約600万円の請求をしていたものの,傷害についての治療費,慰謝料等は既に支払われているものとして請求が棄却され,全く支払を受けることができない結果となっていました。
そのため,控訴を提起して,控訴審(高裁)において,なんとか第1審の判決を覆してほしいとの依頼でした。
◆ 事件の解決
1 一般的に,第1審の判決を控訴審で覆すことができるのは1割程度で,3割程度は何らかの形で和解,6割は原審どおりと聞いています。
したがって,私は依頼人に対して,その事実を告げたうえ,「一般論としては,第1審の判断を覆すのは困難である」と伝えましたが,依頼人としては,「どうしても納得できない」ということでした。
また,私自身も,1審の判断には疑問があったことから,ご依頼を受けることになりました。
2 原審の認定のポイントは,
① 初診の時,「腰椎捻挫」の診断がない
② 依頼者が「腰痛」を訴えたのが,本件事故から10日後である
③ レントゲン検査の結果,腰椎の変性は認められたものの,下肢について,痺れなどの異常所見はなかった
などの根拠をあげて,「腰椎捻挫」と本件事故との因果関係を否定したものでした。
その結果,私としては,本人の供述等から,
・ 依頼人に,手足の痺れなどの症状が現れていたこと
・ 依頼人の仕事が,トンネルの現場点検作業という特殊な仕事のため,直ちに現場を離れて通院することができなかった事情
・ レントゲン撮影の翌日には,MRIの撮影も行っていること
・ その後,依頼人は仕事を辞めざるを得ず,長期間,病院に通院した事実
などをあげて,「腰椎捻挫」と後遺障害の因果関係に絞って主張しました。
3 その結果,高裁では,いったん結審した後,裁判官から双方に対し,
「加害者は被害者(依頼人)に対し300万円を支払う」という内容で,和解の指示がありました。
この「和解案」は,依頼人の「腰椎捻挫」と後遺障害の因果関係を認めることを前提としたものです。
依頼人としては,金額的には不満があったものの,因果関係を認めてもらったということで納得し,当方は和解を受けることとなりました。
4 しかし,加害者の代理人(実際は,保険会社の依頼のもとに,加害者の代理人となった弁護士)は,これを拒否したため,判決となりました。
5 その結果,「遅延損害金(交通事故の場合,事故発生日から,損害額に対して年5分の割合の遅延損害金がつくことになります。)を含め,約330万円の支払を受ける」ことができる判決も出してもらいました。
◆ 弁護士のコメント
1 控訴審(高裁)で原審の判決を覆したり,実質的に原審の判決を覆すような和解をすることは,一般的には困難です。
したがって,あまり「控訴審から依頼を受ける」ということはしないようにしています。
しかし,この時は,依頼人が,「どうしても控訴したい」という強い気持ちを持っており,私自身も「判決」を読ませてもらい,疑問に思うところがあったことから,受任することになりました。
2 なお,控訴審における和解については,「納得できない」として和解を受けなかったとしても,和解で示された案とほとんど同じ結果となる判決が出されるのが,一般的です。
また,高裁の判断に納得ができないとしても,上告(最高裁)はさらに狭き門なので,よほどのことがない限り,高裁の和解勧告には従うほかないというのが私の経験からの結論です。
もちろん,「耐えがたきを耐え,忍びがたきを忍び」というような状況の時もあります。
但し,本件では,相手方が和解を蹴ったことにより,相手方は約30万円多く負担しなければならないことになりました。
3 さらに,最近,交通事故事件では,加害者側の代理人弁護士(実質的には,保険会社が依頼した弁護士)は,訴訟において,「徹底的に争う」という姿勢で臨んできます。
これは保険会社の方針と思われますが,海外者側は,医師の「意見書」や様々な専門的な論文を提出するなどして,事故と損害の因果関係を否定することに力を注いでいます。
「被害者の症状は,事故とは関係ない」とか「この程度の事故で,このように重い受傷をすることは,物理的に有り得ない」などの主張をよく見かけます。
私の個人的な見解ですが,保険会社は,交渉による示談の場合の金額より,裁判による判決の金額が相当程度高くなることが通例であるため,何とか訴訟提起を抑制しようと,あらゆる事件において,可能な限りの反論をしているのではないかと考えざるを得ません。